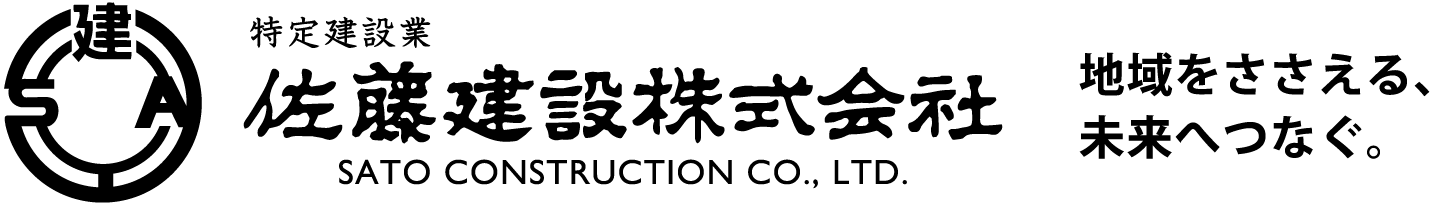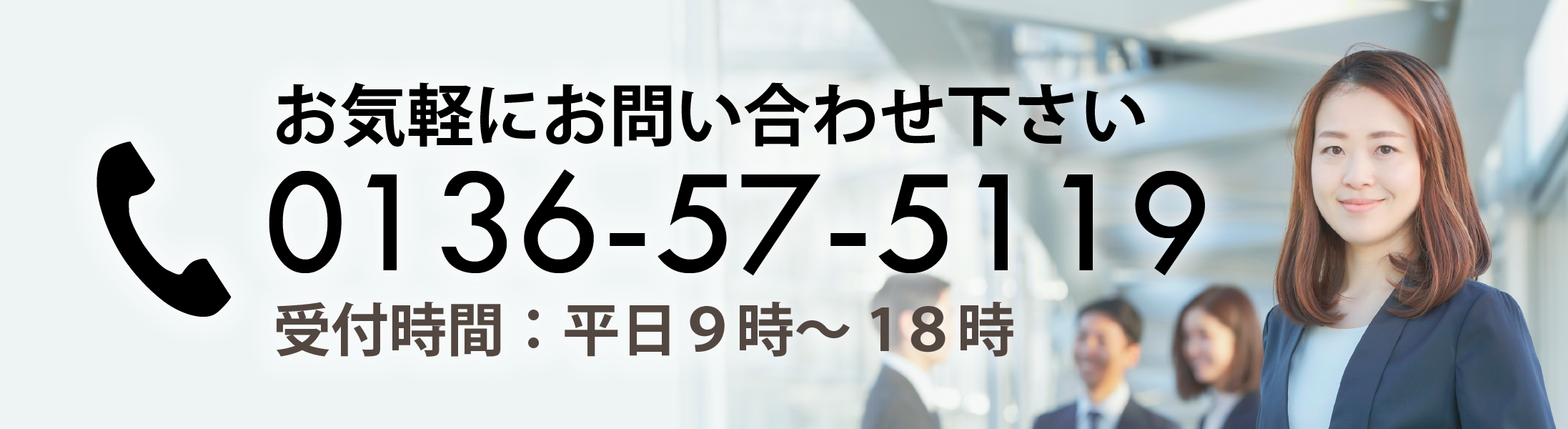農業農村整備工事とは
農業農村整備工事とは、農業の生産性向上と、農村地域の生活環境の改善を目的として行われる、農業用施設の整備や地域基盤の構築を支える土木工事のことです。
これらの工事は、日本の食料供給を支える農業の振興と、過疎化・高齢化が進む農村の持続的な発展に欠かせない社会インフラ整備の一環です。
主な農業農村整備工事の種類
1. ほ場整備工事
農地の区画を整え、用排水や農道などを整備する工事です。田畑の形状を整えることで、農作業の効率化や機械化が可能となり、生産性が大幅に向上します。
2. 用水路・排水路工事
農業に必要な用水の安定供給と、余分な水の速やかな排水を実現するための施設整備です。コンクリート水路やパイプライン、暗渠排水なども含まれます。
3. 農業用ため池の改修・築造工事
農業用水を貯めるためのため池を新たに築造、または老朽化により改修する工事です。水源の確保や水不足対策、地震・大雨への安全対策にも重要な役割を果たします。
4. 農道整備工事
農作業車や運搬車両の通行を目的とした農道の整備です。舗装や幅員の確保により、農産物の輸送効率が改善され、農業経営の安定化に貢献します。
5. 基盤整備関連構造物工事
揚水機場、分水施設、ゲート設備、調整池などの農業インフラを構築・更新する工事です。これらは精密な水管理と灌漑(かんがい)システムに不可欠です。
6. 中山間地域対策工事
傾斜地や地形条件の厳しい農村において、階段状の農地整備(棚田保全)や斜面対策、地すべり防止施設の整備を行う工事です。
農業農村整備工事の目的と意義
農業農村整備工事は、単に「農地を整える」ためだけでなく、地域の暮らしを支える包括的なインフラ整備として、以下のような重要な役割を担っています。
- 農業の生産性向上と担い手支援
ほ場整備や農道整備により、機械化・効率化を促進。若手農業者や法人経営の活躍を支えます。 - 農村地域の防災・減災
ため池や排水路の改修は、豪雨・台風時の浸水・決壊リスクを低減し、安全な生活環境を守ります。 - 環境保全と景観維持
水路やため池の再整備は、自然環境の保全や美しい農村景観の維持にもつながります。 - 地域活性化と住民福祉の向上
インフラが整備されることで、住民の生活の質が向上し、地域への定住促進にもつながります。
当工事の施工上の特徴
- 農作業の時期を避けた工程調整が求められ、短期間での高精度な施工が必要
- 自然環境・生態系への配慮が重視される
- 地元農家や関係機関との調整・協力が欠かせない工事である
このように、農業農村整備工事は、日本の「食」と「地域」を守るうえで、非常に重要な役割を果たしています。当社では、これらの工事においても豊富な経験と確かな技術で、安全かつ丁寧な施工を行い、地域の発展に貢献してまいります。
主な工事受注実績
| 日付 | 工事名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成 10年 | 土地改良総合整備三和地区第31工区 | 北海道北海道後志支庁 |
| 平成 10年 | 農地保全整備芙蓉地区第1工区 | 北海道後志支庁 |
| 平成 11年 | ほ場整備(高度利用)下梨地区第2工区 | 北海道後志支庁 |
| 平成 14年 | 中山間(一般)こぶしの郷外1地区第3工区 | 北海道 |
| 平成 15年 | 経営体育成基盤整備 福井地区 第1工区 | 北海道 |
| 平成 17年 | 経営体育成基盤整備共和西部地区第41工区 | 北海道 |
| 平成 17年 | 畑総(担い手育成)赤井川地区第3工区 | 北海道 |
| 平成 19年 | 経営体育成基盤整備共和西部地区第1工区 | 北海道 |
| 平成 19年 | 中山間(生産基盤)ほたるの里地区第5工区 | 北海道 |
| 平成 20年 | 中山間(生産基盤)富岡地区第1工区 | 北海道 |
| 平成 22年 | 中山間(生産基盤)富岡地区 第31工区 | 北海道後志支庁 |
| 平成 23年 | 中山間(生産基盤)富岡地区第22工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 平成 24年 | 農地防災下梨野舞納地区 第32工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 平成 26年 | 中山間大谷地区62工区 | 北海道後志総合振興局産業振興部農村振興課 |
| 平成 27年 | 中山間 富岡地区 1工区 | 中山間 富岡地区 1工区 |
| 平成 28年 | 中山間 大谷地区 41工区 | 北海道後志総合振興局産業振興部農村振興課 |
| 平成 29年 | 経営体宿内地区61工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 平成 30年 | 中山間昆布地区41工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 令和 元年 | 経営体 蘭越地区 41工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 令和 2年 | 経営体 初田地区 41工区 | 北海道後志総合振興局 |
| 令和 3年 | 経営体 初田地区 42工区 | 北海道後志総合振興局 |