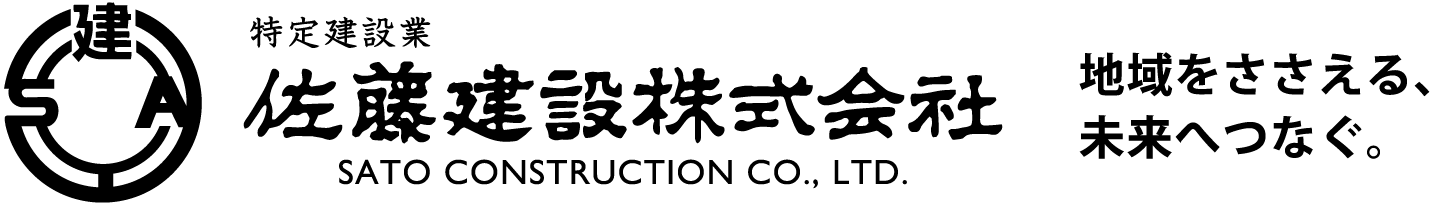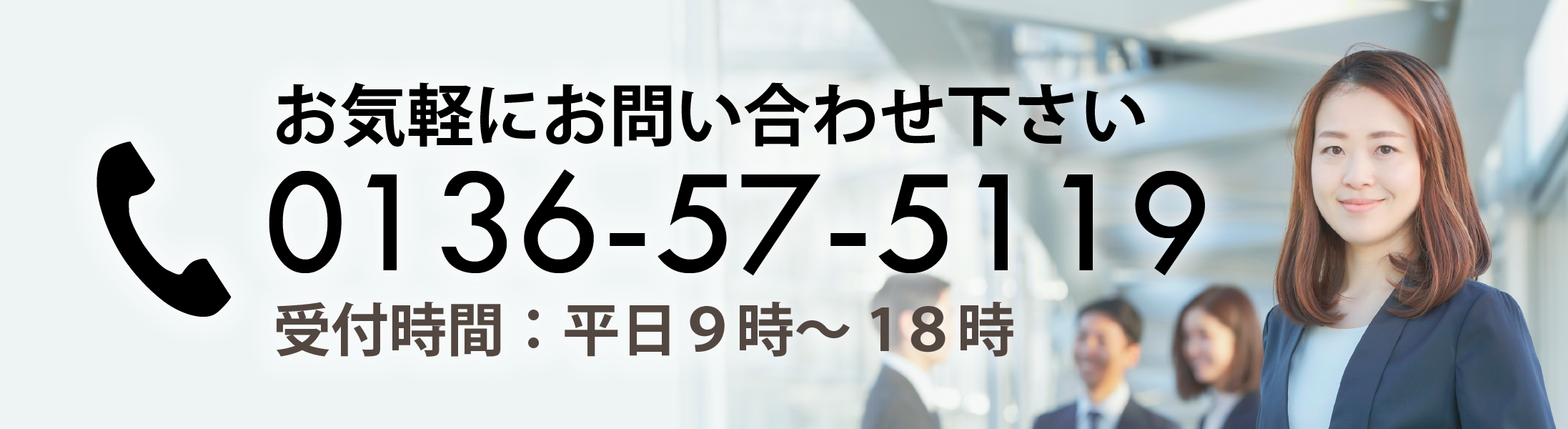海岸工事とは
海岸工事とは、台風や高潮、波浪、津波などによる被害から人々の暮らしや社会インフラを守るために行う、海岸線の整備・保護に関する工事です。日本は四方を海に囲まれ、海岸線の総延長は約3万5千kmに及びます。そのため、防災・減災の観点からも、海岸工事は極めて重要な社会基盤整備のひとつです。
また、海岸は単なる防災の対象だけでなく、港湾・漁業・観光・環境保全など多様な機能を持っており、それぞれの目的に応じた工事が行われています。
主な海岸工事の種類
1. 護岸工事
高潮・高波などの影響を受けやすい沿岸部に、コンクリートやブロック、石材などで護岸を築造・補強する工事です。波の力を分散・吸収し、背後の住宅地や施設、農地などを保護します。
2. 離岸堤(りがんてい)工事
海岸から少し沖に防波堤を設置し、直接波が岸に届かないようにする工事です。波のエネルギーを弱め、浸食を防ぎます。
3. テトラポッド設置工事
波浪の衝撃を減衰させるため、テトラポッドなどの消波ブロックを設置する工事です。護岸や堤防の前面に配置されることが多く、構造物の破損防止にもつながります。
4. 人工リーフ・潜堤工事
水面下に構造物を設置して波をコントロールする工事です。自然景観を損なわず、環境負荷の少ない方法として注目されています。
5. 海岸侵食対策工事
砂浜が波によって削られてしまう「海岸侵食(かいがんしんしょく)」を防ぐため、砂の補充(養浜)や人工構造物の設置を行います。
6. 津波・高潮対策工事
堤防や水門の強化・嵩上げなどを行い、万が一の津波・高潮時に被害を最小限に抑えるための工事です。
海岸工事の目的
海岸工事は以下のような目的で行われます:
- 住民の生命・財産を守る
高波や津波、高潮などによる災害から、住宅・施設・農地・漁港などを保護します。 - 重要インフラの保全
道路・鉄道・港湾・電力施設など、社会を支えるインフラを波浪・侵食から守ります。 - 自然環境や生態系の保全
干潟や砂浜などの自然環境の保全・再生を目的とした工事も行われます。 - 観光資源の保護
砂浜や景勝地など、観光資源としての海岸の維持にもつながります。
施工上の特徴と留意点
- 気象・海象の影響が大きい:風・波・潮汐など、自然条件による制約が多いため、高度な施工管理と計画性が必要です。
- 海中・水際の施工技術:潜水作業や特殊な重機を用いた工事など、専門的な技術・装備が求められる分野です。
- 環境への配慮:生態系への影響を抑え、景観や自然との調和を重視する設計・施工が求められています。
地域における海岸工事の意義
沿岸地域では、海と共に暮らす文化・産業が根付いています。海岸工事はそれらを守り、災害に強いまちづくりと、持続可能な地域社会の実現に貢献します。近年では、「多機能型海岸整備(防災・環境・利用)」が注目されており、単なる防災施設ではなく、人と自然が共生できる空間の創出も視野に入れた設計が増えています。
| 日付 | 工事名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成 10年 | 軽臼漁港海岸局部改良工事 | 北海道 |
| 平成 10年 | 軽臼漁港海岸局部改良工事2工区(補正) | 北海道 |
| 平成 14年 | 栄浜海岸(道単)局部改良工事 | 北海道 |
| 平成 17年 | 原歌海岸(歌島地区)高潮対策工事外 | 北海道 |
| 平成 21年 | 盃海岸外(道単)局部改良工事 | 北海道後志支庁小樽土木現業所 |
| 平成 23年 | 珊内漁港海岸(道単)局改工事(道債) | 北海道後志総合振興局 小樽建設管理部 黒松内事業所 |
| 平成 24年 | 珊内漁港海岸(道単)局改工事(道債) | 北海道後志総合振興局 小樽建設管理部 黒松内事業所 |
| 平成 25年 | 珊内海岸(道単)局改工事(道債) | 北海道後志総合振興局小樽建設管理部黒松内事業所 |